







待降節について
典礼暦上の一年の始まりです。主の降誕 (12月25日)の4つ前の日曜日から主の降誕の前晩のミサの直前まです。(待降節は11月30日、もしくはそれに近い主日の「前晩の祈り」にはじまり、主の降誕の「前晩の祈り」の前に終了します。
待降節を守る習慣は、5世紀ころからはじまったといわれています。主の公現の祝日までの40日間を四旬節の期間にならっていました。
後に、キリスト誕生の準備期間とされ、現在の4つの主日になりました。カトリック教会は、待降節をキリストが誕生された日、クリスマスを待ち望み準備する期間として過ごします。また、待降節の前半は、終末におけるキリストの再臨に私たちの心の目を向けさせる終末的色彩の濃いときでもあります。
歴史は、人間の数限りない神へのそむきと、それにもかかわらずたえず人に回心を呼びかける神のいつくしみとで織りなされていますが、まさに、待降節はこの人間の罪の闇と、いつも人間を受け入れてくれる神の愛のあたたかさのコントラストが最もはっきりしている季節です。
この待降節中に読まれる聖書は、第1朗読の旧約聖書では、救いの日の訪れを告げる預言書が読まれます。第2朗読では、主の再臨を待望するにあたっての教訓、勧告をのべた箇所が読まれます。福音書では、終末における主の再臨や第一の来臨を準備した洗礼者ヨハネの記事などから選ばれています。
待降節の典礼色は紫色です。待降節第3主日には、バラ色を用いることができます。
アドベント・カレンダーやろうそくは、私たちの心にキリストを待ち望むことを呼びかける助けとなっています。
待降節は、アドベント (Advent) は、カトリック教会において、イエス・キリストの降誕を待ち望む期間のことです。日本語では待降節(たいこうせつ)、降臨節(こうりんせつ)、または待誕節(たいたんせつ)といいますが、教派によって名称が異なり、主にカトリックや福音主義教会(ルター派)では待降節、聖公会では降臨節と呼んでいます。
アドベントという単語は「到来」を意味するラテン語Adventus(=アドベントゥス)から来たもので、「キリストの到来」のことである。ギリシア語の「エピファネイア(顕現)」と同義で、キリスト教においては、アドベントは人間世界へのキリストの到来、そして、キリストの再臨(ギリシア語のパルーシアに相当)を表現する語として用いられる。
カトリック教会では、前述の通り1年は待降節から始まるりますが、クリスマスカードの一般的なあいさつに「A Happy New Year.」が使われるのはこの意味からです。
待降節の始まりの日にち(ただし必ず日曜日から)は、その年の12月25日を基準にするため、その年によってが違いますが、11月30日の「聖アンデレの日」に最も近い日曜日からクリスマスイブまでの約4週間で、最も早い年で11月27日、遅い年でも12月3日に始まります。5世紀後半に、クリスマス前の断食の時期として、聖マルティヌスの日が開始日と定められましたが、後にグレゴリウス1世の時代に、4回の主日と定められました。最初のアドベントを待降節第一主日と呼び、その後、第二、第三、第四と主日が続きます。
アドベントには、ろうそくを4本用意して、第一主日に1本目のろうそくに火をともし、その後、第二、第三、第四と週を追うごとに火をともすろうそくを増やしていくという習慣があります。この習慣は、一説によると、ドイツ国内の伝道の祖といわれるJ・H・ヴィヒャーンが始めたもので、ハンブルクにある子供たちの施設「ラウエス・ハウス」(粗末な家)で初めて行われたそうです。当時は、クリスマスまで、毎日1本ずつそうそくを灯したともいわれています。
「アドベントクランツ」(または「アドベントリース」)は、常緑樹の枝を丸くまとめ、装飾したものに、4本のろうそくを立てたものですが、アドベント用に4本のろうそくが立てられる燭台を用いたものもあります。クランツのモミの枝は降誕日を、4本のろうそくは待降節の4回の主日を意味しています。クランツ(冠の意)は称賛や崇敬を表し、王たる存在のイエスを象徴し、常緑樹の緑色は救い主イエスの永遠の命を意味していると言われています。
通常、ろうそくの色は白または典礼色に倣い紫ですが、第三週のガウデテ・サンデイのみはバラ色のろうそくを用いる場合もあるようです。また、家庭においてはろうそくの色は自由であり、実にさまざまなものが存在します。
子供たちの楽しみとしてアドベントカレンダーがありますが、紙や布などで作られ、待降節の始まりから12月25日までの日付の窓やポケットがついており、ポケットに天使やサンタクロースなどの小さなぬいぐるみを入れたり、その日の窓やポケットを開くとイラストが現れたり、お菓子が入れてあったりとさまざまですが、いずれにしてもクリスマスを心待ちにし、敬虔な気持ちで待降節を過ごすことを子どもたちに教えるための待降節の飾りです。また、救い主イエス・キリストの誕生物語(Nativity)をあらわす馬小屋は、待降節には欠かせないものです。
降誕節について
主の降誕の前晩のミサから始まり、「主の洗礼」をもって終わる期間です。
降誕節は、主の降誕(12月25日)の「前晩の祈り」ではじまり、主の公現後の主日(1月7日~13日の間の日曜日)で終わります。
日曜日で必ず終わるので、年によって日にちが移動します。長い時は2週間と6日、短い時は、2週間です。
教会の歴史の中で、「主の過ぎ越し」の記念に次いで、行ってきた最古の祭儀は、「主の降誕と主の公現」の記念です。「主の降誕と主の公現」の記念は、降誕節中に行われます。
主の降誕 12月25日。祭日。伝統的には、前晩(12月24日の日没後)・夜半(25日午前0時)・早朝(25日未明)・日中(25日午前)の4回のミサが行われます。ただし多くの教会では、夜半のミサを24日の晩に前倒しして祝っています。
降誕節は、固有の8日間をもちます。聖家族の祝日(8日間中の日曜日。日曜日がない時には30日)。26日 聖ステファノ殉教者。27日 聖ヨハネ使徒福音記者。28日 幼子殉教者。29~31日 主の降誕第。5日~7日1月1日 神の母聖マリアの祭日です。
1月2~5日の間の日曜日は、降誕後第2主日です。
1月6日は主の公現ですが、日本は守るべき祭日でないので、1月2から8日の間の日曜日に祝います。
主の洗礼の祭日は、主の公現直後の日曜日に祝います。しかし、主の公現の祭日が1月7日か8日にあたる場合、主の洗礼の祭日は、その翌日に祝います。
降誕節の典礼色は白色です。
聖家族について
12月26日~31日の間の主日で、その期間に日曜日がない場合は12月30日。祝日。
クリスマス後の最初の日曜日に聖家族を祝います。8日間の間に日曜日がないときには、30日に祝います。この日、イエスの幼年時代の挿話を聞きながら、家族の意味を考えます。ナザレの聖家族が「福音の学舎」であると呼んだのは、教皇パウロ6世でした。
このナザレの小さな家庭、イエス、マリア、ヨセフに目を注ぎ、彼らをほめたたえるだけの祝日ではありません。彼らの家庭に目を注ぎながら、私たちの家庭を顧みるのです。私たちの家庭が神の愛に満たされるよう、祈り、願い、心を新たにすることが大切です。
神の望んでおられる人類の一致と平和をはぐくむのは、家庭という小さな共同体、最も小さな社会からはじまるのではないでしょうか。聖家族も、イエスの誕生後すぐにエジプトへの避難の旅を余儀なくされました。
心に抱いて祈る、それは大海の一滴の行為かもしれませんが、あきらめることなく、小さな家庭の平和のために祈ることは意義あることです。
第1朗読は、ABC年共通の朗読を読むこともできます。それは、シラ書(集会の書)3章2~6、12~16節です。ここでは、親に対する子のあり方、両親、特に年老いた両親に孝養を尽くすようにと教えています。
B年固有の朗読として読むことができるのは、創世記15章1~6、21章1~3節です。 「子孫を増やそう」との神の祝福をいただいたにもかかわらず、アブラハムとサラには子がありませんでした。しかし、神はこの年老いた夫婦に男の子が生まれるとの約束をします。しかも星のように、と言われます。かの地の空は澄んでいるので、それはそれは数えきれないほどの星です。それこそ満天の星空で、神から外に連れ出されて星を見せられたアブラハムは、何を感じたのか、と思います。
聖書は、「アブラムは神を信じた」とだけ書いています。事実、神は約束を実現されたのです。教会が聖家族の祝日にこの聖書を私たちに指し示すのはどういうことかを黙想しながら、このみ言葉を聞いてみましょう。
ABC年共通の第2朗読では、コロサイの信徒への手紙3章12~21節を読みます。
そこでは、家庭における愛の生活を説いています。夫と妻、親と子がどのような心構えをもって家庭生活を送ったらいいか、キリスト者として新しくなった身分から、全く新しい人間関係、とくに家庭内での新しい秩序についてのべられています。「すべてを完成させるきずなです」とパウロは言います。家庭におもいやり、ゆるしあい、大切にしあう心が大切ですね。聖マザーテレサも言っています。「愛の実践は、まずは家庭から。」と。
B年は、ヘブライ人への手紙11章8、11~12、17~19節が読まれます。ヘブライ人への手紙11章は、旧約の人々がどれほど信仰によって生きたかを語っています。今日の箇所は、信仰の父と呼ばれるアブラハムの生涯から、彼の信仰あふれた出来事を示す箇所が選ばれています。
一つの家庭の中には、いろいろの出来事があるものです。それをどのように自らのうちに受け止め、生きるのか、ヘブライ人への手紙の著者は、この章の冒頭に「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。…信仰によって、わたしたちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは、目に見えているものからできたのではないことが分かるのです。」と言っています。
イエスの幼年時代の家庭生活について語るのは、マタイとルカ福音書だけですが、今年はルカ福音書が読まれます。イエスは両親に伴われて、エルサレムの神殿に奉献のために行きます。そこで、神の救いを待ち望んでいたシメオンとアンナに出会います。ここのカ所は、旧約のサムエル記上1章と民数記6章を読んでみると、イエスの奉献の出来事の意味が理解しやすくなります。
ルカ福音書では、洗礼者ヨハネと出来事とを平行して記していますが、このイエスの神殿での奉献については、ヨハネは書いていません。つまり、ルカはこの出来事の意味をイエスにだけ見ていたということが出来ます。つまり、イエスは神に聖別された人として、「異邦人を照らす啓示の光」として、律法に従ったのだとルカは言っているのです。
「親子は主の律法で定められたことをみな終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。」という2節に描かれている行間に、やがて宣教のために公の生活が開始されるその時までの30年の生活が隠れています。
恵み豊かな父よ、
あなたは、聖家族を模範として与えてくださいました。
わたしたちが聖家族にならい、愛ときずなに結ばれて、
あなたの家の永遠の喜びにあずかることができますように。 (集会祈願より)
-2025 年度 仙台教区 行事予定表-
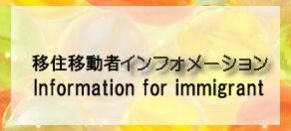











【最終号】
NEW !
Sendai Catholic Diocese Newsletter

「4→6・45通信」は、「国道4号線沿い(内陸部)から国道45号線沿い(岩手~宮城沿岸部)、6号線沿い(福島県沿岸部)への支援」という意味が込められています。
2013年5月から2016年8月まで、月に一度発行しておりました。


仙台司教区内にある小教区の配置図と
地区別に小教区の詳細をご紹介します。
小教区は現在工事中です。
順次掲載してまいりますが、しばらくお待ちください。
福島デスクは福島県内での支援活動の調整や情報発信、地域諸団体との連携のため、2012年12月に設立され、2017年4月に活動を休止しました。その間に発行したニュースレターをご覧いただけます。






◎2024.7.18 日本カトリック司教文書
◎2024.7.16 訃報 首藤神父様の通夜・葬儀予定
◎2024.6.07 2024年度(第三次)司祭人事異動
◎2024.6.07 仙台教区感染症対策について
◎2024.5.26 世界こどもの日教皇メッセージ
◎2024.4.12 アドリミナ動画
◎2024.4.12 バチカンニュース
◎2024.4.12 2024年度教区行事予定表
◎2024.3.13 2024年度司祭派遣人事(第2次)
◎2024.3.2
◎2024.2.19
◎2024.2.14
◎2024.2.10 2024年四旬節教皇メッセージ
◎2024.1.25 新駐日教皇大使任命について
◎2024.01.15
◎2024.01.10 能登地震に関する案内・報告
◎2024.01.01 第57回「世界平和の日」教皇メッセージ
◎2023.12.01 新型コロナウイルス感染症にともなう措置
◎2023.11.24 教会現勢報告調査票
◎2023.11.15
◎2023.10.25
◎愛のあかし元和の大殉教400年記念第1回シンポジウム
◎仙台教区報No.250
◎2023年教区新地区・司祭派遣のお知らせ
◎「教会現勢調査票」について
◎新型コロナ感染症第7波に伴う教区の対応について
◎エドガル司教コロナ感染症、感染について
◎釜石教会70周年記念はがきについて
◎平和を求める祈り
◎法務大臣宛司教要請文:日本を故郷と思っている子供たちとその家族を追い出さないでください
◎在留特別許可嘆願署名キャンペーン
◎第2回「祖父母と高齢者のための世界祈願日」のための祈り(邦訳とEnglish)
◎訃報ケベック外国宣教会司祭ボリュー神父・ベルニエ神父
◎2022年「世界広報の日」教皇メッセージ(2022.04.08)
◎ガクタン・エドガル被選司教司教叙階式・着座式ミサ 動画配信のご案内(2022.03.01)
◎ Appointment of Priests for the Year 2024
◎2023.12.1
◎2023.10.25
◎information
◎mass schdule
◎help desk
(仙台教区人権を考える委員会)
「ニュースレター」として親しまれた本紙も、最終号を皆様にお届けする時を迎えました。3.11のあの混乱の中で、第1号を出したのは、2011年4月30日でした。第1号は「ありがとう。届いています」と皆様からの献金と支援物資が届けられていることをまず、感謝していますが、これは、10年間ずっと続いてきたことでした。ボランティアとして、支援者として、ベースでの奉仕活動をとおして、全国の教会の皆様が被災地に目を注ぎ、いつも温かく支えてくださったおかげで、最終号・145号まで続けることができました。仙台教区サポートセンターは3月31日で閉鎖されますが、各ベースでの支援活動は続きます。これからも、皆様のこれまで以上の支えが必要かもしれません。最後にもう一度、本紙の読者の皆様に心よりの感謝を申しあげます。ありがとうございました。
カトリック仙台司教区へようこそ
12月の典礼 12月7日(日)待降節第2主日 12月14日(日)待降節第3主日 12月21日(日) 待降節第4主日 12月24日(水)・25(木) 主の降誕 12月28日(日)聖家族


仙台司教区 〒980-0014 仙台市青葉区 本町1-2-12 Tel: 022-222-7371 Fax: 022-222-7378 発行責任 広報委員会








All rights reserved to カトリック仙台司教区
Copyright 2013